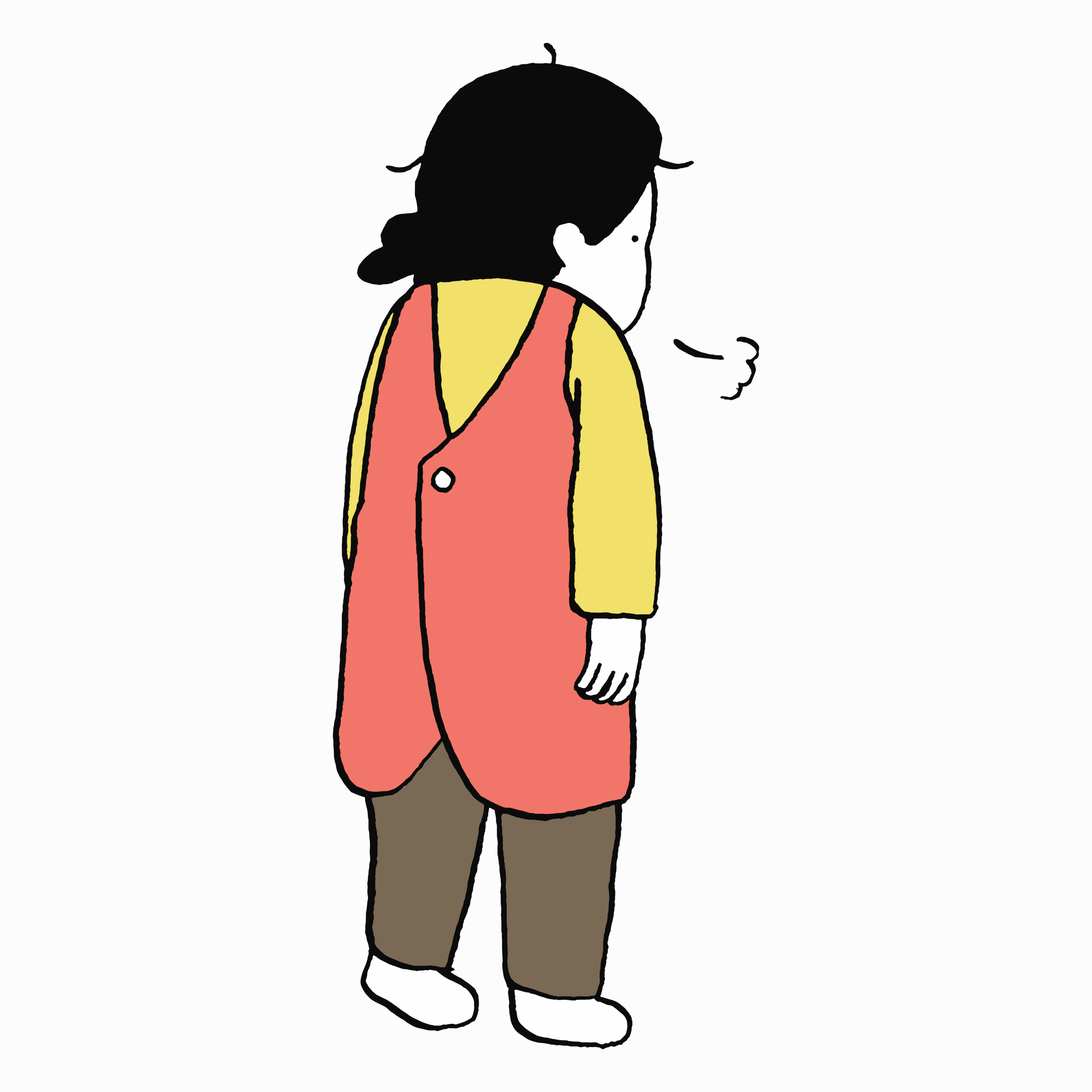私の三女は、3歳児検診まで発達に関する問題に引っかかることはなかったのですが、今思えば、自閉スペクトラム症の特徴が小さい頃から見られる場面が時折あり、発達障がいのグレーゾーンだったと思います。
顕著になったのは5歳頃のことです。
自分の気に入らないことがあると、すぐに癇癪を起こす。
自分だけのルールを大切にし、それから外れると一切受け入れない。
世間一般の「常識」や親の言葉が、まるで届かないような態度を取ることもありました。
親としての戸惑いと苦しみ
一番つらかったのは、癇癪を起こした娘にどれだけ言い聞かせても気持ちが収まらず、どうにもならないことでした。
当初は「強く叱り、抑え込むことが大事なのだ」と思い込み、感情をぶつけ合うような日々を過ごしていました。
しかし、その方法ではますます娘の怒りや涙が激しくなるばかりで、私自身も「育て方が悪かったのではないか」と自分を責め苦しんでいました。
特に、怒りをぶつけられたとき、「もっと強い力で押さえ込まなければ収拾がつかない」と信じ込んでいたところがありました。
学校で気づかされたこと
小学1年生の2学期。登校を嫌がる娘に「がんばって行きなさい!」と励まし、無理やり学校へ送り出したことがありました。
その日、担任の先生から電話があり「学校へ来てもずっと泣き続けていて、気持ちが落ち着かず大変でした。落ち着いてから登校させてください」と言われました。
上の二人の娘は、家では不機嫌でも学校に行けば友達と会って気分が変わる子どもでした。その感覚をそのまま三女に当てはめてしまった私は、「このやり方は違う」と痛感し、大きな反省をしました。
自閉スペクトラム症の子どもが「できないこと」
自閉スペクトラム症の子どもは、決して「わがまま」や「甘え」でできないのではありません。
脳の特性として、環境の変化や想定外の出来事に強いストレスを感じやすく、そのため感情のコントロールが難しくなるのです。
正直なところ、三女が自閉スペクトラム症と診断される小学3年生まで、どう対処すればよいのか分かりませんでした。
「うちの子は発達障がいなのだろうか?」と疑ってもいいのかどうか、何とも言えない気持ちを抱えながら過ごしていたのです。
専門機関でしっかり調べてもらい、臨床心理士さんや医師から専門的なお話を伺うことで、改めて我が子の特性を理解することができました。
そのときに一番強く感じたのは、「一人で悩まず、専門家や周囲の人に相談することで、子育てに光を見出せる」ということでした。
この気づきがあってから、私自身の関わり方も少しずつ変わっていったのです。
「寄り添うこと」が一番の支え
癇癪を起こしているとき、親が上から抑えつけるのではなく、
「何に不満を感じているのか」
「どんな気持ちで怒っているのか」
を、まず受け止めようと努めました。
もちろん、興奮している間は言葉が届きません。
だからこそ「落ち着いたら聞かせてね」という態度を示し、水を飲ませたり呼吸を整えさせたり、物理的にクールダウンさせる工夫をしました。
そして冷静になったタイミングで、改めて「どうして怒ってしまったの?」と聞き、理由を一緒に探っていきました。
それを繰り返すうちに、少しずつ「気持ちを言葉で伝える練習」にもなっていきました。
子育ての中で感じたこと
子育ては本当に難しいものです。特に発達の特性を持つ子どもとの毎日は、思い通りにならず悩むことも多いでしょう。
それでも、親だからこそ「根気強く」「何度でも寄り添える」力があるのだと、私は三女との日々から学びました。
自閉スペクトラム症の子どもたちに必要なのは、一般的な「正しさ」や「常識」を押しつけることではなく、その子の気持ちを理解しようとするまなざしだと思います。
寄り添う姿勢こそが、子どもに安心を与え、少しずつ成長を支えていく大切な支えになると実感しています。
もちろん、ここでお伝えしたのはあくまでも私自身の子育ての体験であり、それがすべての方に当てはまるわけではありません。お子さんによって、特性の表れ方や困りごとはさまざまです。
それでも私の経験が、どなたかが気づきを得るきっかけになれば幸いです。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。